”仕事を辞めたい。でも怖くて上司に言い出せない。”
”退職代行をお願いしたら「コソコソ隠れていないで出てこい!」と責められた。だから行きたくないんだって。。。”
そんなふうに悩む人がたくさんいます。
誰だって会社を辞めるときは自分の口できちんと伝えたいものです。
それができないくらいに追い込まれていたり、ストレスを感じている。
だから専門家に任せて手続きしようとしているのに、逆に責められてしまう。
 くまた
くまた本当に困っている時、誰かに助けを求めるのに責められるのはおかしなことです。
・常識がない、非常識
・バックれただけじゃないか?
どんな辞め方をしても、文句を言う人はいますし、カンペキな退職手続きってありません。
退職理由が人間関係やパワハラ、長時間のサービス残業などが原因なら、まずはあなたの心と体を全力で守ることが何より大切ですよね。
心や体を犠牲にしてまで働き続ける意味も価値もないんですから。
退職代行を使うか使わないかは自分で決めればいいこと。
ただ使う際にはこの記事で解説したポイントを確認してください。
この記事で解説すること・お伝えしたいことは次の3つです。
①退職代行を使う人が増えている理由やネットで批判される理由
②なぜ批判を気にする必要がないのか
③退職代行を使ってスムースに退職するための準備
退職代行を使うことはクズなんかじゃない

大前提として退職は民法で定められた労働者の権利です(民法627条)。
上司が気に入らない、残業が多すぎる、セクハラされたなど、どんな理由でも辞めたければ辞めて良いんです。
僕も会社の規則に沿って退職手続きを進めることを否定する訳ではありません。
「同僚や会社・顧客に迷惑をかけずに辞めたい」、そんな気持ちは尊いですし、次のキャリアに取ってもプラスになります。
ただ、あなたが心身ともに疲弊していたり、身の危険を感じているなら、何も遠慮することなく退職代行を活用しましょう。
心身ともにボロボロなのに無理に直接会社に行って、上司や人事に伝える必要はないんですよ。
 くまた
くまた僕はひろゆき氏の意見に賛成ですね。
会社視点で考える退職代行の利用
会社視点で言えば、バックれて何の連絡もないぐらいなら、どんな手段でも退職の意思表示をしてもらった方がはるかに助かります。
後任を選ばなければいけませんし、採用やお客さまへの説明も必要になる場合だってありますから。
知らせがないまま時間だけ過ぎるのが、あなたにとっても会社にとっても一番良くないやり方です。
退職したい口にしたら、あっという間に噂は広まり退職しずらい空気になってしまいます。
一発勝負ですので確実に退職できる方法を選んでください。
注意してほしいのは、法律的に退職代行業者ができることできないことが決まっていることです。
退職代行を使う人が増えているのはなぜか?
退職代行を使いたいと考える人が置かれているのは次のような状況です。
ギリギリまで追い詰められているなら、誰かに助けを求めるのは自然で当たり前のことじゃないですかね?
退職代行をクズだと批判する人たち
退職代行をクズだと批判する人たちは、無責任・甘えだと倫理観や責任感から非難してきますよね。
確かに管理職の立場からすれば、事前に相談してくれるとありがたいです。
でも、信頼関係もなく、ハラスメントが常態化しているような職場なら、「常識」を期待する方が間違っています。
問題は、こうした職場では「常識」を振りかざす人ほど非常識になっていると言うことですね。
だから「気にする必要はない」んです。
あなたの人生、キャリアを取り戻すために、堂々と退職代行を利用してください。
退職代行を使うデメリット
冒頭に書きましたけど、文句を言う人はどんな形でやめたって文句を言います。
そうした外野の声は気にしないことが一番。
 くまた
くまたとはいえ、例外的にデメリットになるパターンがあることは覚えておいてください。
それは、会社がすごくホワイトで、業界内でも上位、取引先・顧客も多く、同じ業界で転職すると何らかの関係が続く可能性が高い場合です。
この場合は、同じ業界ないで転職するとあなたの評判=キャリアにマイナスになる可能性が出てきます。
できれば避けたいところです。
そのためには今の会社がブラックでもホワイトでも、スムースに辞めるポイントがありますから最低限そこを押さえておきましょう。
スムースに退職するための3つの準備

誰からどんな文句を言われ、非難されようとも、やっておくと後々得する可能性のある準備はあります。
ここでは特に大切なポイントを3つとできればやった方がいいポイント1つを紹介します。
絶対に同僚には相談しない
避難や文句は無視すればいいとは言っても耳に入ってくればあまりいい気持ちはしませんよね。
おとなしい方はそれだけですごくストレスを感じてしまうかもしれません。
そんな外野のヤジを少しでも押さえたいなら、転職・退職することは絶対秘密にしておくべきです。
たとえどんなに仲が良くても、できるだけ秘密にしておくことをお勧めします。
社内規則の確認
普通の会社であれば、退職についての社内規則があるとおもいます。
社内規則に縛られて転職できない・退職できないと言うことはありません。
でもトラブルの可能性を事前に潰しておく点でも社内規則には目を通しておきましょう。
私物の整理
もし会社で個人用のロッカーや机を支給されている場合、社歴が長いほど私物ってたまりますよね?
問題が起こってからでは遅いので、会社のロッカーや机の引き出しに私物を保管しているなら念の為チェックしておきましょう。
 くまた
くまた特に三文判(ハンコ)などを保管しているなら要注意です。
悪用されないように必ず持ち帰っておきましょうね。
また、メモ帳やノートがどこにどれくらいあるかも大切な確認ポイントです。
仕事で使っていても、つい書き殴ってしまうグチや顧客情報、仕事で使うIDやパスワードなどがあるかもしれません。
中身を確認しておくことをお勧めします。
紙類は廃棄する場合もシュレッダーにかけるなど、十分注意してくださいね。
できるだけ引き継ぎ資料を作成して情報を整理しておく
パワハラで退職するような場合は緊急度が高く私物の整理や引き継ぎを十分にする時間がないと思います。
引き継ぎ資料の作成や後任者が困らない程度に情報をまとめておくとあなたの信用を少しだけ守ってくれます。
できる範囲で準備しましょう。
例えばあなたしか使わないIDとパスワードなど。
月次や週次の締めに必須でそれがないと会社の売上に悪影響が出てしまうような場合は、退職後に損害賠償請求をされるリスクがあります。
自分がいなくなった後に何が起こるのか、どんな影響があるか、それは会社や顧客に損害を与える可能性があるのかについては確認して、対策の準備をしておきましょう。
「英語を使ってグローバルな仕事にチャレンジしたい」「GAFAのような大手外資系企業で働いてみたい」という方は外資系IT転職の進め方をステップ・バイ・ステップで解説していますので、ぜひ参考にしてください。

退職代行についてよくある質問

退職代行サービスに関するよくある質問をまとめてみました。
退職代行サービスごとに対応できるものとできないものがあります。
詳細については利用予定の退職代行サービス会社に確認してくださいね。
Q1. 退職代行サービスの申し込みで聞かれることは?
一般的には、以下のような項目です。
Q2. 退職代行を使えば、確実に辞められるのか?すぐに?
どんな場合でも確実にすぐやめられるとは限りません。
雇用契約は正社員のような「期間の定めのない労働契約」と契約・派遣社員やパートなどの期間の「期間定めのある労働契約」の2種類があります。
「期間の定めのない雇用契約」の場合は、民法627条によって、あなたから退職の申し出をすれば、その日から14日経過後退職となります。
ただし、離職票発行で会社と揉めたくない場合は、就業規則に沿った退職手続きをとる必要があります。
契約・派遣社員やパートなどの期間の「期間定めのない労働契約」の場合、原則として契約期間中は働かなければなりませんが、やむを得ない場合など一定の例外が認められています。
Q3. 退職代行を申し込んだ後に、自分がしないといけないことは?
Q1で解説したあなたと会社に関する情報をまとめておくことです。
また、すぐに転職したいなら並行して転職活動を進める必要がありますよね。
転職活動の流れを知りたい場合は、こちらの記事も参考にしてください。

次にどんな求人があるかを知りたいなら、転職サイトや転職エージェントを利用することをお勧めします。
成功率を上げて効率的に転職活動を進めるための転職エージェントの組み合わせ方については「目的別おすすめ転職エージェントランキング【転職成功率を上げる組合せ方】」も参考にしてください。
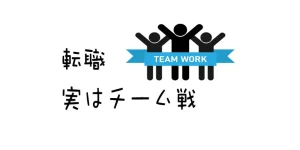
Q4. 失業保険に必要な離職票はどうやって手に入れるの?
離職票は「雇用保険被保険者資格喪失届」が正式名称ですが、失業保険金を受け取るために必要です。
退職代行サービスで代理で受け取ってもらうこともできますし、郵送で依頼をかけることもできます。
雇用保険被保険者証、資格喪失連絡票、源泉徴収票なども同様です。
あなたの希望・都合に合わせて退職代行サービスに相談してください。
Q5. 退職代行サービスは、弁護士と労働組合のどっちがお勧め?
退職代行サービスは、以下の3つのパターンがあります。
退職に関わる手続きや会社との交渉には、弁護士資格が必要なものがいくつか含まれる場合があります。
「非弁行為」と呼ばれるもので、弁護士や労働組合でない一般企業が、弁護士を代理人とせずにこの行為を行うことは禁止されています。
具体的には会社と揉めた場合の代理・仲裁・和解など、法的な交渉が発生する場合ですね。
悪質な企業が退職代行サービスを提供していることもありますので、次のような資格を持った退職代行サービスを選んでください。
Q6. 退職代行サービスは、私物の郵送・宅配も会社に依頼してくれるの?
対応してくれる退職代行サービスがほとんどです。
ただし、会社によっては追加料金となるケースもありますから、詳細は必ず確認してください。
また、どんな私物があって、どれを送り返してもらいたいのか、どれは廃棄しても問題ないのかを一覧にして伝えておくと後々のトラブルを避けることができますよ。
Q7. 退職代行サービスの値段はいくら?追加料金は?
退職代行サービスの費用は、大体3万円前後です。
すでに解説した通り、金額だけではなくて弁護士資格の有無なども比較検討して決めてくださいね。
Q8. 会社から本人に電話は来ないの?
退職代行サービスからあなたに電話をかけないように伝えても、守られるとは限りません。
ただ、電話に出る必要はありませんから無視で問題ありません。
退職に必要な手続きの代行・対応は退職代行サービスに任せましょう。
Q9. 有休消化ってできるの?
有給休暇は、社員の都合で取得できる休暇です。
有給休暇が残っていれば、当然退職時に利用する権利があります。
こちらの申請についても退職代行サービスで対応してくれますよ。
Q10. 退職金ってもらえるの?
就業規則に退職金規定を定めている場合は支払い義務がありますが、基本的に任意で定める制度なので、必ずもらえるとは言い切れません。
就業規則に定めていても、退職金の減額や支給しない場合についても定めている場合があるからです。
もらえる場合も、退職のタイミング(勤続年数の条件を満たすか、など)含めて、就業規則と労働契約書を確認した上で、退職代行サービスに相談してください。
この点からも労働組合や弁護士による退職代行サービスを選ぶことをお勧めします。
Q11. 派遣・契約社員でも退職代行サービスを使えるの?
使えますが、Q2で解説した通り、派遣・契約社員は「期間の定めのある労働契約」で、基本的に契約期間中は退職できません。
現在の雇用形態、契約期間やその他の条件を確認して退職代行サービスに相談してください。
参考:退職に関わる法律
参考までに退職に関わる法律がどうなっているのかを解説しておきます。
① 一般的な正社員の雇用契約は「期間の定めのない雇用」に該当し、退職希望日の2週間前までに申し入れをすれば、2週間経過後に雇用契約は終了します(民法第627条)。
② 1年更新の契約社員は「期間の定めのある雇用」に該当し、契約更新の6ヶ月前に申し入れをする必要があります。半年更新の契約社員の場合は、退職希望日の3ヶ月前に申し入れをする必要があります(民法第627条)。
民法第六百二十七条 【期間の定めのない雇用の解約の申入れ】
出典:e-Gov「民法」より
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
③ 職場でのハラスメントや賃金の未払いがある場合、会社が法令違反をしている場合、本人・家族の病気で働くことが難しい場合は、「やむを得ない事由による雇用の解除」に該当し、直ちに契約を解除することができます(民法第628条)。
民法第六百二十八条 【やむを得ない事由による雇用の解除】
出典:e-Gov「民法」より
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
④ 退職の意思表示を会社に伝えるだけであれば民間の代行業者で対応できますが、有給休暇の取得や即時退職を希望する場合は会社との交渉が発生しますので、弁護士資格が必要になり、民間の退職代行業者では対応できない場合があるので注意してください(弁護士法第72条)。
弁護士法第七十二条 【非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止】
出典:e-Gov「弁護士法」より
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
退職の準備と並行して転職活動も始めよう

退職の準備が整ったら、並行して転職活動も進めてください。
手元資金に余裕があっても、いずれ転職して働く必要がありますよね。
ブラック企業を選んだり、ハラスメントにまた合わないように十分な時間をかけて情報を集めて、納得のいく会社を選びませんか?
質の高い求人のほとんどは非公開で早い者勝ち。
目的別に無料でキャリア相談ができる転職エージェントを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ 退職を決めたなら迷わず退職代行サービスを使おう

もう一度結論から。
あなたなりの理由があって退職を決めて、直接会社や上司に伝えたくないなら迷わず退職代行サービスを使いましょう。
退職した後に広がる新しいチャンスを思えば、外野のヤジなど気にする必要もない。
いつどこでどんなことを決めても結局は自分に返ってくる。
それなら、思うがままに決めたほうが人生楽になると思いませんか?
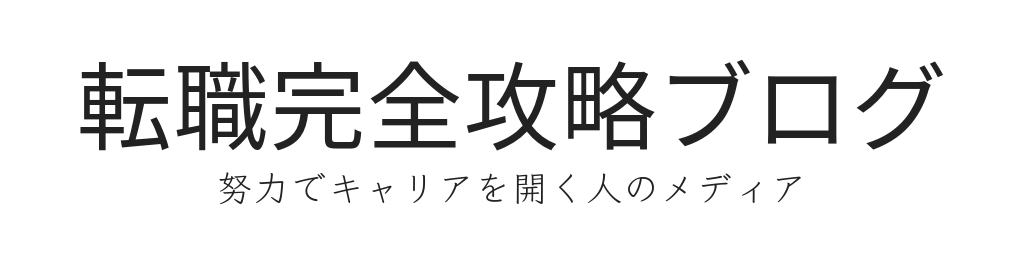
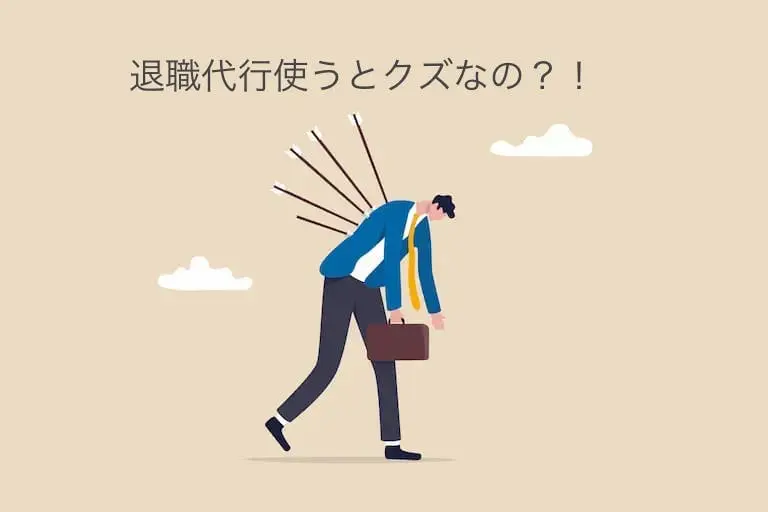
コメント